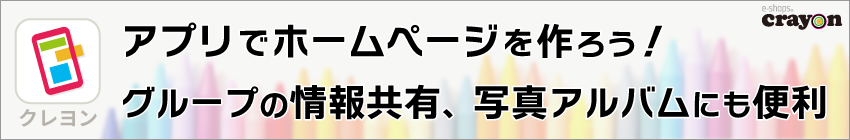
例えば、54歳の人が高次脳機能障害になったら、脳梗塞やくも膜下出血などの脳の病気では回復の過程で医療や介護保険や精神自立支援サービスを利用することが出来ますが、事故(交通事故や転倒等)では、医療と精神自立支援サービスは受けられても、介護保険を利用できません。
何が大きく違うかというと、回復過程での日中の居場所の選択肢です。
高次脳機能障害が軽度で、社会復帰出来たり、家事などが出来るまでに回復した方は別として、見守りや介助が必要な方の日中の過ごし方で、家族には大きな違いが出てきます。
想像してみて下さい。
家族の誰かが病気やけがをして、その介護で仕事を辞めなくてはならない。障害がなかなか良くならず、入れる施設もなく、在宅そしてその介護がいつ終るか分からない。
同じ経験者の仲間が必要です。
どうやって乗り越えたのかを知っているのは、経験者。
食事の時に、ご飯、お味噌汁、焼き魚、お漬物、冷奴がテーブルに並んでいると、ご飯だけをひたすら食べる。終わると焼き魚を食べるといった、1品づつを食べていく『ばっかり喰い』をする。
顔を洗うつもりで洗面台の前にたったら、光るものが目にはいり、そこが気になって顔を洗わないで、じっと立っている。
椅子から立っておトイレに行くつもりが、コーヒーカップが目にはいり、また座ってコーヒーカップを持ってしまう。
何か気になると、そこから離れられない。
5分前の事も覚えていない
過去の想い出を全く覚えていない
家族も分からない
事故後に毎日家族の写真を見せて、父・母・妹・妻・子供の写真を見せながら、家族と説明したから、過去を思い出したのかは分からないが、家族であることはなんとなく分かったらしい。
家族がいるから、記憶が無くても心配していないと本人は言っています。
思ったことが言えない
文章を読んでも意味が分からない
字を書けない
話せないけど、字や文章を書くことが出来る事もあります。作家神足さんです。
頭の中で地図を書くことが出来ないから、家から出たら家に帰ってこれない
家の中でも何度も行っているトイレが分からなくなる
例えば、左半側空間無視だったら、物の左半分が見えてはいるけれど、認識出来ないから、お皿に乗っている左半分には手を出さない。
簡単に言うと、動作の真似が出来ない
前のページでも書きましたが、その物が何であるか分からない。
簡単に言えば、喜怒哀楽が激しい。
変なときに笑い出すのも困りますが、怒りが止まらない方が恐いです。(脱抑制)
社会的ルールに違反している事を許せない。
順番が分からない。
例えば、料理の順番が分からない。
材料を揃えるー洗うー切るー焼くー盛り付ける
等の順番が分からない。
自分の障害に気付いていない
脳挫傷の慢性期で「まわりくどい話がとまらない」症状
①話がまわりくどい(迂遠)
②場にそぐわない話題
③自分の事を一方的に延々と話す
④聞き手の不快感を考慮しない
1 遂行機能障害
会話成立させるには相手の要求を常に認識している必要がありますが、それが出来ません。
2 情動の認知障害
他人の情動的な信号(表情や声の抑揚等)を理解出来ない。
3 言動の自制の欠如
会話や流暢性は保たれるが、意味が伝わりにくく話題が次々に移り、話す内容が、抑制をかけている。また、話を終らすタイミングがみつからない。